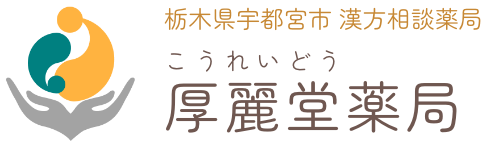朝起きるのがつらく、立ちくらみや頭痛、動悸に悩まされる。

学校に行けない日が続き、午後からは元気でも、朝になるとまた体調が悪くなる
このような症状が見られる場合、起立性調節障害(OD)の可能性があります。
起立性調節障害とは?
起立性調節障害は、主に思春期の子どもに見られる自律神経の不調による病気です。
血圧や心拍の調整がうまくできず、立ち上がると血圧が急に下がる、
逆に血圧が急に上がる、脳に十分な血液が送られずに貧血のような症状が出るなど、多くの体調不良を引き起こします。

主な症状
朝起きられない
立ちくらみ、めまい
動悸や息切れ
頭痛、全身のだるさ
食欲不振(特に朝)
夜に元気になり、寝つきが悪い
イライラしやすく、集中力が低下
病院で検査を受けても、血液検査やMRIでは異常が見つからないことが多いため、
「怠けているのでは?」と誤解されることもあります。
しかし、これは自律神経の乱れによる病気であり、決して気のせいではありません。
西洋医学の治療とその課題
一般的に、起立性調節障害の治療では昇圧剤(血圧を上げる薬)が使われることがあります。
しかし、すべての患者に効果があるわけではなく、頭痛や動悸などの症状が十分に改善しないケースも少なくありません。

また、起立性調節障害にはさまざまなタイプがあり、血
圧が下がるもの、逆に上がるもの、血圧に変化がないものなど、症状が一律ではありません。
そのため、一般的な薬では対応しきれないことが多いのです。
漢方が有効な理由
西洋医学では「血圧」や「脈拍」に注目して治療しますが、
漢方では「体全体のバランス」を整えることを重視します。
起立性調節障害の子どもたちを観察すると、多くの場合、以下のような特徴が見られます。
成長のエネルギーが十分に発揮されていない
自律神経のバランスが崩れ、血流が不安定になっている
消化器が弱く、栄養をうまく吸収できていない
漢方では、これらの問題を個別に見極めながら治療を行います。
つまり、「血圧を上げる」ことだけに注目するのではなく、
「体の成長を促し、本来のエネルギーを引き出す」ことを目的とします。
起立性調節障害に用いられる漢方
起立性調節障害の治療では、体質に合わせた漢方薬を選ぶことが大切です。
代表的な処方には以下のようなものがあります。
① 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
立ちくらみやめまい、動悸がある場合に用いられる処方。水分代謝を整え、自律神経のバランスを改善します。
② 五苓散(ごれいさん)
むくみや頭痛が強い場合に使われます。体内の水分バランスを調整し、スッキリとした目覚めを促します。
③ 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
疲れやすく、食欲がない場合に適しています。胃腸を元気にし、体力を回復させる働きがあります。
④ 小建中湯(しょうけんちゅうとう)
冷え性で、胃腸が弱く、エネルギー不足の子ども向け。消化機能を改善し、体を温めます。
⑤ 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)
めまいや頭重感が強い場合に用いられる処方。特に胃腸が弱い子に向いています。
症例紹介
ケース1:中学1年生の男の子
部活の怪我の後、朝起きられなくなり、昇圧剤を服用するも改善せず。漢方治療を始めて3ヶ月後、朝スムーズに起きられるようになり、体力も回復。
ケース2:冷え性の中学2年生の女の子
頭痛とめまいで朝起きられず、夜には口の中が熱くなるという症状があった。漢方で体のバランスを整えた結果、朝の不調が軽減。
まとめ
起立性調節障害は、西洋医学だけでは治療が難しいことが多く、漢方によるアプローチが有効です。
当店では、お子さまの体質に合わせた最適な漢方を提案し、根本的な改善を目指します。
お子さまの健やかな成長を漢方の力でサポートいたします。
気になる方は公式LINEからご連絡お待ちしております