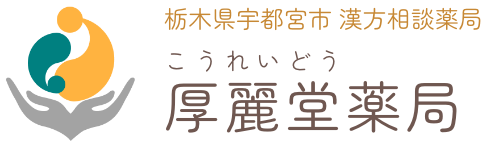お子様のメンタルを心配されている親御さんこんにちは。
梅雨が近づいてくると、
「なんだか子どもの様子がおかしいな」と感じる親御さんが増えてきます。
朝起きられない、イライラしやすい、元気がない…。

それ、ただの「だるさ」ではなく、東洋医学でいう“湿邪(しつじゃ)”の影響かもしれません。
今回は、梅雨時期に増えやすい子どもの心身の不調について、漢方の視点から解説します。
⸻
◆梅雨に注意したい「湿邪(しつじゃ)」とは?
湿邪とは、空気中の湿気や、体の中にたまった余分な水分が原因で起こる不調のこと。
特に日本の梅雨は「高温多湿」のダブルパンチで、体が重だるくなりやすい季節です。
中医学では、湿邪の特徴をこのように捉えます:
•重だるさ:体が重く、頭もボーっとしやすい
•粘り気:症状が長引きやすく、スッキリしない
•下にたまりやすい:足腰がだるい、下痢などの症状が出やすい
•エネルギー(気)の流れを妨げる
特に、消化吸収をつかさどる「脾胃(ひい)」が弱いと湿邪の影響を受けやすくなります。

⸻
◆心のバランスにも影響する湿邪
中医学では「心(しん)は神(しん)を蔵す」と言われ、
心の状態が穏やかであれば、思考・感情・睡眠も安定すると考えます。
湿邪が心をおびやかすと、子どもにはこんな変化が出てきます:
•授業中に集中できない
•すぐにイライラしたり、落ち込んだりする
•活動する意欲が湧かない
•寝つきが悪く、眠りが浅い
特に思春期のお子さんは、心と体が大きく揺れる時期なので、影響が出やすくなります。

⸻
◆起立性調節障害(OD)と湿邪の関係
最近ご相談が増えている「起立性調節障害」も、この湿邪と大きく関わっています。
朝なかなか起きられない、立ちくらみ、頭痛、だるさ…。
現代医学では自律神経の乱れとされますが、中医学では以下のように考えます:
•脾虚湿困(ひきょしつこん):脾胃が弱り、湿邪が体内に停滞
•清陽不昇(せいようふしょう):頭へスッと気が上がらず、めまいや集中力低下に
•気虚(ききょ):湿邪が長引き、体力や気力をどんどん消耗してしまう状態
このように、中医学では「気・脾胃・湿邪」の関係に注目しながら、根本的なサポートをしていきます。
⸻
◆おうちでできる中医学的ケア
毎日取り入れられる「梅雨の養生法」をご紹介します。
【1】食事で湿邪を追い出そう
•余分な湿を排出する食材:はとむぎ、もやし、冬瓜、緑豆、とうもろこしのひげ茶
•脾胃を元気にする食材:山芋、かぼちゃ、にんじん、小米(あわ)
•控えたいもの:冷たい飲み物、甘いもの、脂っこい料理、乳製品(とりすぎ注意)
【2】生活習慣でバランスを整える
•朝ごはんは必ず食べる(脾胃のリズムを整えます)
•軽い運動で汗をかく
•部屋の湿度は50〜60%に、除湿・換気も大切
【3】ツボケアで体のめぐりをサポート
•足三里(あしさんり):胃腸を元気に
•豊隆(ほうりゅう):湿を排出
•百会(ひゃくえ):頭の巡りをよくしてスッキリ
⸻
◆漢方薬という選択肢も
体質や症状に応じて、漢方薬も有効です。
よく使われる処方例としては…
•勝湿顆粒:外から入った湿気による不調に
•六君子湯:胃腸が弱く、湿がたまりやすい子に
•温胆湯:イライラや不安、不眠がある場合に
※体質や状態に合った漢方を選ぶことが大切です。必ず専門家にご相談ください。
⸻
◆おわりに:梅雨の不調は「予防」がカギ!
湿邪による不調は、梅雨が始まる前からの予防がとても大切です。
脾胃のはたらきを整えて、湿に負けない体づくりをしておけば、
心も体もゆらぎにくく、穏やかに毎日を過ごせます。
もし「最近、子どもがちょっと元気ないな…」と感じたら、
ぜひお気軽にご相談くださいね。
東洋医学の視点から、お子さんの心と体に寄り添ったご提案をさせていただきます。